[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
東北出身ですし、その後、北京、ミシガンで暮らしましたから、
暑いより寒いほうが過ごしやすいのですが、
蘇州の寒さには慣れません。
といはいえ、暑いよりはまったくいいです。
家の中の暖房は、オイルヒーターとエアコンなのですが、
今日はオイルヒーターだけ使って、室温14℃。
あまり温度を上げると、今度は空気が乾燥しますしね....
部屋が日本よりも広い分、温まらないんです。
そして湿度も上がらない。
これでも加湿器つけているんですよ!
それでもなかなか湿度があがらない!!
ちなみにモコモコといろいろ着ています。
下着2枚に、フリース着て、その上にキルティングの袖なし、そして首にマフラー。
足は、タイツと靴下にレッグウォーマー。
そんな現在の外の様子は
どちらもさきほど写したスクリーンショットなのですが...
どちらが正確なんでしょうねぇ...
~>゜)~<蛇足>~~
オイルヒーターの前から離れないクジャ。
そして作ったもの...
・ジンジャービネガー なんのことはないショウガと酢をブレンダーにかけたもの。(400gのマヨ瓶一つ分)
・青唐辛子の酢漬け 青唐辛子を刻んで酢につけただけ... (400gのマヨ瓶一つ分)
・紅白なます スライサーを使うのでこれまた簡単にできるし... (500グラムほどの大根を使いました)
・豆もやしのナムル ゆでて、ゴマ油などと混ぜるだけ... (豆もやし350g分)
そこまでつくって、寒い中のキッチンで体が冷えてしまい、作業中止!
(キッチン、寒いんですよ!!!(>_<))
ほかにトマトケチャップ、ドレッシング、タコミートとか作りたかったんですけどね。
体が冷えた作業後、生姜入りホットコーラで体を温めました(*^^*)
そういえば明後日(22日)は冬至だと思いいたりました。
立冬のころ、もう冬になるのねぇ... と思ったのですが、
その後ぼんやりと過ごしすぎました (^^ゞ
日本では冬至カボチャといいますが、
中国では冬至には餃子を食べます。
かぼちゃの餃子を食べる地方もあるとか...
(いつでも餃子じゃないの?という突込みはなしにしてください。)
(私もそう思っています... (^▽^))
かぼちゃの餃子...
日本の方には不思議かもしれませんが、
中国にはいろいろは具の餃子があります。
たいていは一種類の野菜と肉です。
我が家の子供たちが小さいころ、お気に入りは人参の餃子でした。
色もきれいだし、甘みがあっておいしいんですよ。
私は中国セロリが好きです。
でもやっぱり白菜の餃子が無難ですね...。
三鮮という3つの種類の具材+肉の餃子もあります。
昔は、どどど~~~んと餃子を作ったものですが、
(一度に数十個)
最近は怠け者で冷凍ものを買っています。( -_-)
当たりはずれのない白菜と肉の餃子がほとんどです。
もちろん作るのは水餃子。
スープ餃子...? 邪道です。
スープにするならワンタン(馄饨)です。
話がそれてしまいましたが、
冬至には春待ちのイベント「消寒図」の準備をしたいです。
冬至から9日x9回で春を待つのですが、それを「数九(九を数える)」といいます。
「消寒図」は、九弁の梅や、九画の漢字を使った句を用いるのですが、
お天気を書いていく夏休みの宿題のようなものもあります。
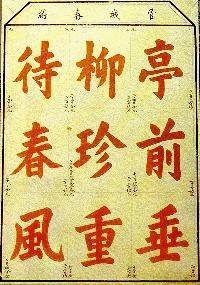
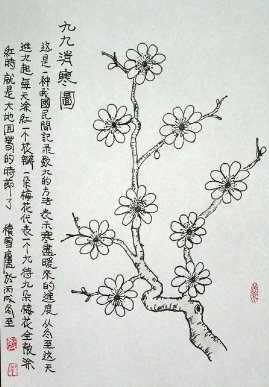
この「数九」には数え歌のようなものもあります。
一九、二九はまだまだだ序の口だ。
三九、四九で犬猫が凍え死ぬ。
五九、六九で柳が芽吹き、
七九で川の氷がとけて、八九で雁がとんでくる。
九九八十一で畑仕事。
おおざっぱにはこんな感じでしょうか。
冬至から9x9= 81日後(「出九」といいます)
実は私の誕生日だったりその前後です。
なのでもう年を重ねるのは嫌な私ですが、
冬の間ばかりはは、誕生日が待ち遠しく感じます。(^^ゞ
~>゜)~<蛇足>~~
メインサイトの「消寒図」、「数九」も参照いただけたら嬉しいです。
~>゜)~<蛇足2>~~
北京住まいが長かった我が家ででは餃子は、最低でも50個は作りました。
水餃子はおかずではなく、主食です。
餃子の日は、餃子+おかず(野菜の炒め物)などという食卓になります。
そして余った餃子が、あくる日、焼き餃子で復活します。
餃子をつけるのは、香醋(中国の黒酢)のみ。
ニンニクは餃子には入れません。
という記事を読みました。
ほうじ茶ラテは試したことがありませんでしたが、
おいしそうですね!!
今度作ってみよう!!!
そういう私は
プーアル茶ラテをたまに飲んでいます(^^ゞ
緑茶ラテの存在を知って、その後、いろいろな中国茶で作ってみて、
これはOKと時々作っているのが「プーアル茶ラテ」。
なかなかいけますよ!
興味のある方は試してみてください。
(レシピなんてありません。お茶をプーアル茶にするだけです。)
